|
 チャットボットを導入する際に、「全体呼量の〇%を削減する」というざっくりとした目標を設定してしまうと、効果が見えづらくなります。「チャットボットを入れたことで、入電数を削減できた!効果が出た」と言えるためには、どの問い合わせ内容(コールリーズン)を、チャットボットで自動対応することにしたか、を明確にしておかないと分析しようがありません。
チャットボットを導入する際に、「全体呼量の〇%を削減する」というざっくりとした目標を設定してしまうと、効果が見えづらくなります。「チャットボットを入れたことで、入電数を削減できた!効果が出た」と言えるためには、どの問い合わせ内容(コールリーズン)を、チャットボットで自動対応することにしたか、を明確にしておかないと分析しようがありません。
コールリーズンごとに分解して、「そもそもチャット対応に向いているのか?」「オペレーターによる有人チャットが良いのか?」「チャットボットで自動化が適してるのか?」……とステップに従って考えていくことが大切です。その積み上げで得た効果こそが「全体呼量の何%が削減できた」という結果に繋がります。
オンライン通販のお客さま窓口を例にステップを考えてみます。コールリーズンを問い合わせ件数の多い順番に並べると、①配送状況など注文内容の確認、②定期購入に関わる手続き、③ログインに関する問い合わせ、④製品に関する問い合わせ、この順番で多かったと仮定します。
なお、コールリーズンが取れていない場合は、WebのFAQ検索結果順位などが参考になります。
続いて、どのコールリーズンに取り組むかを見定めます。すべてのコールリーズンがチャット対応に適しているわけではありません。基本的には呼量の多いコールリーズンから検討を進めていくのですが、例えば、②の「定期購入に関わる手続き」で「解約したい」という問い合わせは、コールセンターでオペレーターが丁寧にヒアリングするなど人が電話で受ける方が、解約を防げる可能性が高まると考えられます。こういったコールリーズンは、最初からチャット化対応のリストから外すという判断もあり得ます。
各コールリーズンに関わる「オペレーション」を分解していくことで、どのコールリーズンを優先的に取り組んでいくのかを決めていきます。順番は、「電話対応の見直し」「オペレーターによる有人チャット対応」「チャットボットによる自動化」「システム連携による自動化」、このように検討していきます。
いきなりチャットボットの導入を検討するのではなく、順番に沿って、それぞれの段階で、どのような施策が可能かを分析していくことがポイントです。
チャットボットやシステム連携などを進めるほど初期投資がかかるため、それだけの ROI のインパクトが出るかを見定めながらの導入をお勧めしています。例えば①の配送状況確認で考えてみます。「有人チャット対応で効率化できるか?」⇒注文番号をもとにドライバーを含めた配送状況の確認が必要なので、お待たせ時間も含めてチャット対応が理想的です。次に、「チャットボット化できるか?」⇒個々の注文番号による確認が必要なため、システム連携を行わない限り自動化は無理。ただし、必ず聞かないといけない点は一律なので、初期ヒアリングはボットで聞いておくことはできます。オペレーターチャットでの折り返し対応が理想的です。最後に「システム連携による自動化はするべきか?」⇒現在のコール数ではシステム連携による全自動化は ROI が出ないので、やらない。
以上の流れで、コールリーズンごとに、ステップを踏んで検討していくことで効果の出るチャットボット導入に繋がります。
(掲載:CCAJ News Vol.291)
|

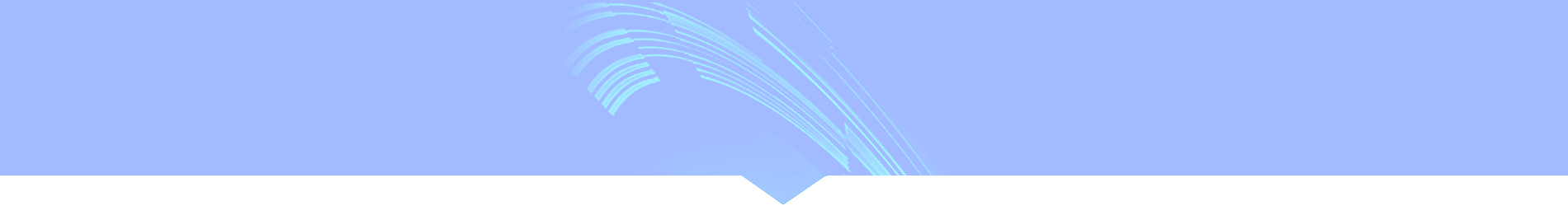
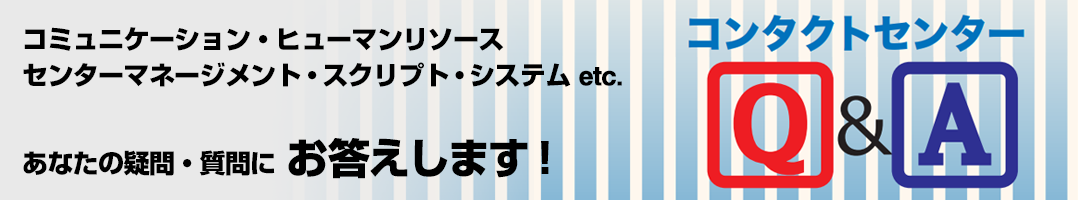
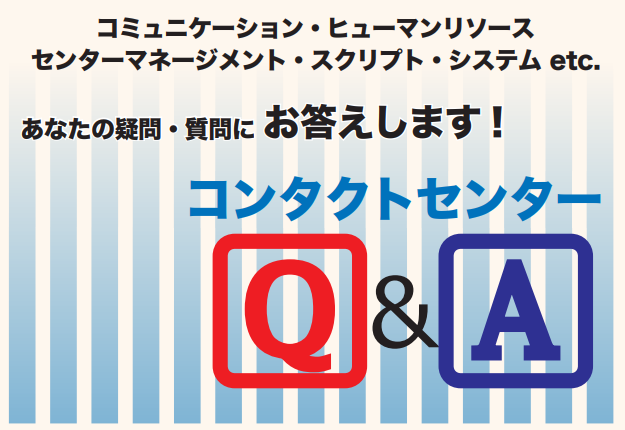
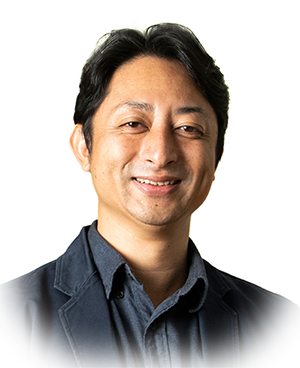
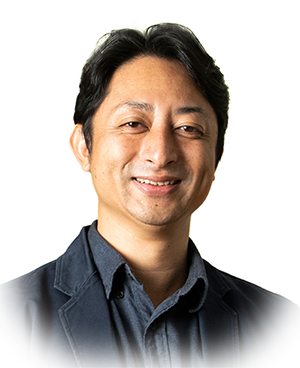

 以前、チャットボットを導入していましたが、呼量も減らず、効果が出ているのか分からず閉じてしまいました。新たにチャットボット導入を検討しています。チャットボットで効果を出すために、導入時に気を付けた方がいいことはありますか?
以前、チャットボットを導入していましたが、呼量も減らず、効果が出ているのか分からず閉じてしまいました。新たにチャットボット導入を検討しています。チャットボットで効果を出すために、導入時に気を付けた方がいいことはありますか?
 チャットボットを導入する際に、「全体呼量の〇%を削減する」というざっくりとした目標を設定してしまうと、効果が見えづらくなります。「チャットボットを入れたことで、入電数を削減できた!効果が出た」と言えるためには、どの問い合わせ内容(コールリーズン)を、チャットボットで自動対応することにしたか、を明確にしておかないと分析しようがありません。
チャットボットを導入する際に、「全体呼量の〇%を削減する」というざっくりとした目標を設定してしまうと、効果が見えづらくなります。「チャットボットを入れたことで、入電数を削減できた!効果が出た」と言えるためには、どの問い合わせ内容(コールリーズン)を、チャットボットで自動対応することにしたか、を明確にしておかないと分析しようがありません。