|
 コールセンターにおいて KPI は非常に重要なツールであり、コールセンターをマネジメントするうえで必要不可欠なものです。管理者であれば KPI マネジメントは必須のスキルと言えます。
コールセンターにおいて KPI は非常に重要なツールであり、コールセンターをマネジメントするうえで必要不可欠なものです。管理者であれば KPI マネジメントは必須のスキルと言えます。
KPI は業務を可視化するためのツールであり、現在、過去のコールセンターの運営、パフォーマンス状況を確認・判断するために使われます。
KPI を使うためには、まず個々の KPI を理解する事が重要です。単純に各 KPI の名称を覚えるのではなく、そのロジックをしっかり頭に入れる必要があります。どの KPI を見れば生産性、品質を確認する事ができるか理解していれば、現状把握、あるいは分析するのが容易になります。よって、まずは各 KPI のロジックをしっかり習得して下さい。
次に、KPI 同士の相関関係、あるいは体系をしっかり理解する必要性があります。
例えば応答率が悪化しているとしたら、応答率を構成する KPI を見る必要性があります。インバウンドセンターであれば、入電予測精度、欠勤率、平均処理時間(以下AHT= Average Handling Time)、平均処理件数(時間あたり)等が構成する KPI になります。また、AHT は平均通話時間(以下 ATT= Average Talk Time)と平均後処理時間(以下 ACW= After Call Work)に体系(分解)化できます。
では、どのように分析したら応答率の原因にたどり着けるでしょうか。原因を究明するには根本となる KPI から確認していく事が大切です。つまり川上より確認していきます。まずは川上である入電予測精度がどうであったか確認する必要性があります。入電予測よりも実際の入電数(30分 /60 分 / 日単位)は多かったのか、少なかったのか、あるいは予想通りだったのかを見て、もし入電数が多かったという事であれば、入電予測精度が低かったため要員不足を招いていたのが大きな要因となります。もし入電予測精度が高かったとしたら、次に予想必要要員数に対してシフトはその通り作成できていたのか、またシフトは必要要員数通り作成できていたとしても、当日の欠勤率はどうだったのか確認をすれば、要員配置による要因が確認できます。それも問題なかったとしたら、次は AHT、平均処理件数(時間あたり)はどうだったのか、想定よりAHT が長く、平均処理件数(時間あたり)が少なければ、入電予測数、要因配置が正しくても、処理能力の問題で応答率を悪化させていた事となります。さらに言えば、AHT が長かった要因はATT なのか、ACW なのか原因を細分化できます。
このように、KPI レポートを活用するためには、センターを運営する管理者が KPI ロジック、KPI 同士の相関関係、体系を理解したうえで、分析方法を知る必要性があります。
(掲載:CCAJ News Vol.255)
|

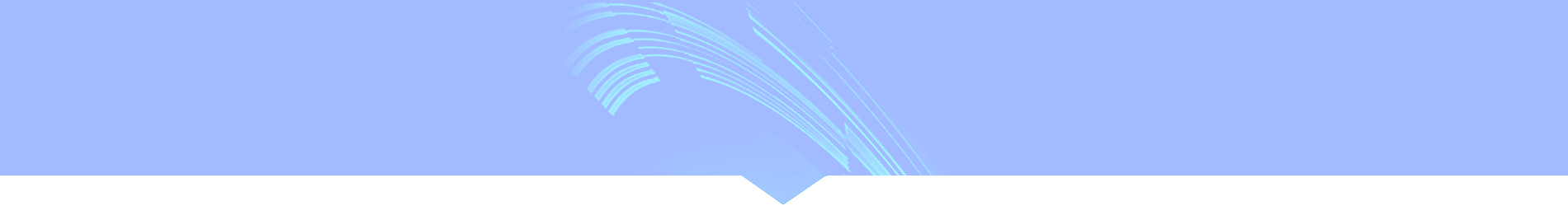
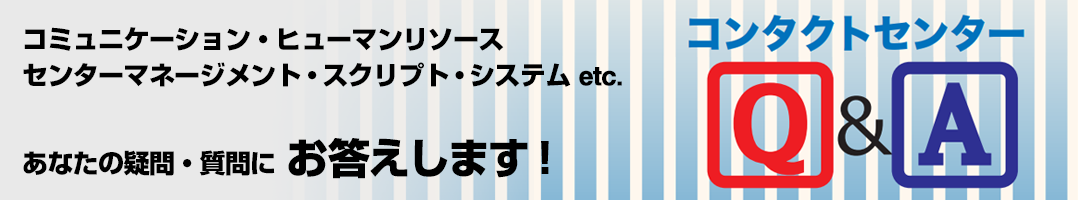
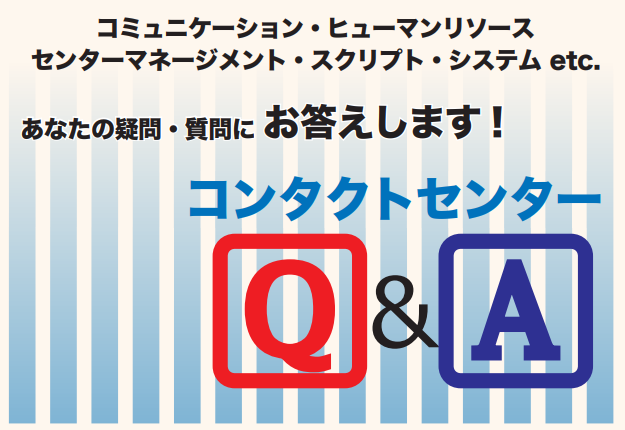



 コールシステム(CTI)からは様々な KPI レポートを取得する事が可能ですが、具体的な活用方法が分からず、業務に活かせていません。どのように活用したらいいのか教えてください。
コールシステム(CTI)からは様々な KPI レポートを取得する事が可能ですが、具体的な活用方法が分からず、業務に活かせていません。どのように活用したらいいのか教えてください。
 コールセンターにおいて KPI は非常に重要なツールであり、コールセンターをマネジメントするうえで必要不可欠なものです。管理者であれば KPI マネジメントは必須のスキルと言えます。
コールセンターにおいて KPI は非常に重要なツールであり、コールセンターをマネジメントするうえで必要不可欠なものです。管理者であれば KPI マネジメントは必須のスキルと言えます。